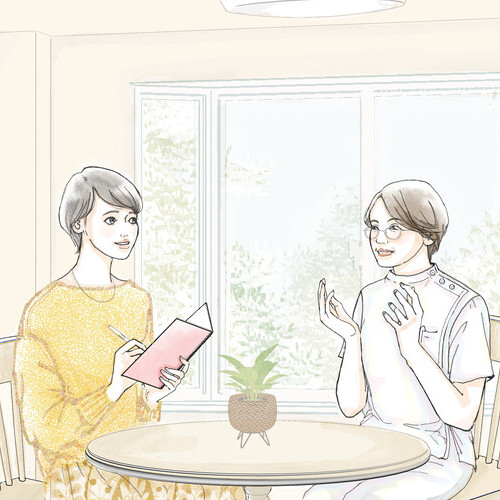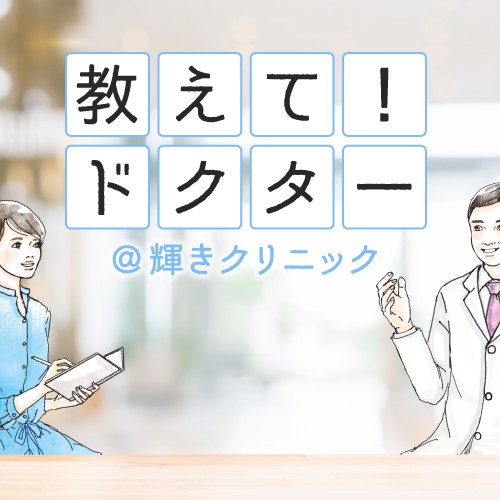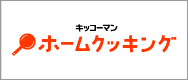夜中に目が覚めて体が熱いのは更年期?睡眠中のホットフラッシュへの対処方法
更新日: 公開日:

ご相談内容
ももりん様(49歳)
睡眠中の寝汗がひどく、特に明け方には寝汗で何度も目が覚めます。予防法や心がけがあれば教えてください。
回答
ももりん様、この度はご相談いただきありがとうございます!寝汗がひどく睡眠中、何度も目が覚めてしまうとのことですね。睡眠の質も下がり、疲れもたまりがちなのではないでしょうか?さぞお困りのことと思います…。
更年期(閉経の前後5年間、おおむね45~55歳の時期)にさしかかると、女性ホルモンの量が波打つようにゆらぎながら減少していき、この急激な変化に伴う自律神経の乱れが原因となり、発汗の症状が気になる方が多くいらっしゃいます。
発汗やホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)などの血管運動神経症状は、更年期の代表的な症状の一つです。ホットフラッシュは実際には昼間だけでなく、夜中も同様に起こるため、睡眠時にもほてりや発汗が起こります。就寝中に、体が熱く感じ何度も目覚めてしまうことで、入眠障害や熟眠障害となる恐れもあります。
参考記事:ホットフラッシュと不眠には深い関係が?
女性ホルモンの減少による不調自体のピークは、平均で2~3年、長くても5年ほどで治まるものとはいわれますが、お悩みが強く、日中の生活に支障をきたす場合などには、婦人科の受診もおすすめします。
今回は、ご質問いただいた「寝汗の予防法や心がけ」につながるセルフケアとして、食事面や日ごろの習慣で工夫できることをご紹介いたします。
★生活習慣の見直し
まずは、朝・日中・夜の過ごし方のポイントをご紹介します。規則正しい生活を送ることは、自律神経のバランスを整えるため、更年期症状の軽減が期待できます。また、睡眠の質の向上にもつながります。
●朝
決まった時間に起き、太陽の光を浴びて、朝食でエネルギーを補給しましょう。
●日中
昼食をしっかり食べ、軽い有酸素運動を取り入れながら活動的に。
●夜
夕食は、遅くとも就寝2時間前に摂りましょう。食事量は軽めがおすすめ。照明を暗めにして、リラックスして過ごしましょう。
ここから、それぞれの時間帯での過ごし方に挙げている食事面のポイントや、取り入れたほうがよい運動、注意したい習慣、睡眠環境などについて、詳しくご紹介していきます。

★大豆イソフラボンを補う
更年期特有の悩みは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た作用をする大豆イソフラボンを摂ることで、緩和することが期待できます。
大豆イソフラボンは豆腐、納豆、豆乳などの大豆製品から摂ることができます。一日の摂取目安量の上限は、70~75mgといわれています。
具体的な食品で見てみると
・豆腐1/3丁(100g)で約20mg
・納豆1パック(50g)で約37mg
・豆乳コップ1杯(200ml)で約50mg
の大豆イソフラボンが含まれています。
大豆イソフラボンは、日々コツコツと摂ることがおすすめです!一定の量の大豆食品を毎日食べることが大変な場合には、サプリメントを活用されるのも良いと思います。
★トリプトファンを摂る
トリプトファンは、眠りを誘うメラトニンを体内で作るのに役立ちます。
メラトニンは、起床して朝の光を浴びた約15時間後(就寝予定時間の約1~2時間前)から増加し、眠気を誘う働きをします。一方、朝の明るい光によって、日中は分泌が抑制され、メラトニンの量は少なくなります。
こうしたメラトニンの分泌により、睡眠と覚醒のリズムが整えられるといえます。つまり質の良い睡眠のためには、規則正しい生活をし、メラトニンの分泌リズムを崩さないようにすることが大切です。
このメラトニンは、神経伝達物質のセロトニンから作られます。セロトニンは、通称「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神状態の安定に関与しています。セロトニンが低下すると、攻撃性が高まったり、不安やうつ・パニック症(パニック障害)などを引き起こすといわれています。また近年、セロトニンの低下の原因に女性ホルモンの減少が関係しており、更年期障害とも関わりがあることが分かりました。
セロトニンを増やし、さらにメラトニンを作るためには、必須アミノ酸のトリプトファンが欠かせません。トリプトファンは、たんぱく質が含まれる食品から摂取することができます。あわせて、トリプトファンからセロトニンを合成するには、「ビタミンB6」も必要です。
トリプトファンやビタミンB6が含まれる食品は、特に朝食で摂ることをおすすめします。玄米ご飯、豆腐のみそ汁、焼き魚や肉、卵焼き、納豆、おひたしなどの副菜が揃った、理想的な和食セットが、快眠に役立ちそうです。
●トリプトファンを豊富に含む食品
・大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)
・乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルトなど)
・卵
●ビタミンB6を豊富に含む食品
・赤身肉
・魚介類
・バナナなどの果物
・玄米などの穀類
★テアニンを摂る
快眠に良い成分として、気分を落ち着かせる効果があるテアニンの摂取もおすすめです。
リラックスしているとき、私たちの脳からはα波という脳波が発生しています。テアニンを摂取すると、このα波が増えることが分かっています。つまり、α波の発生を促進することで、寝つきがよくなることが期待できます。
さらにテアニンは、抑制系の神経伝達物質の活動を促す一方、興奮系の神経伝達物質を抑えます。このことからも、テアニンは睡眠を促す成分だと考えられています。
テアニンは緑茶などに含まれるほか、食品での摂取が難しいときにはサプリメントで手軽に摂ることができます。
★日中の運動習慣
日中に適度な有酸素運動を行うことも、自律神経のバランスを整え、夜間のホットフラッシュを緩和する効果が期待できます。
なぜなら、有酸素運動によって適度な負荷がかかることで、自律神経の機能が向上し、体温調節機能も改善されるからです。また、血行が促進されることで、全身の細胞に酸素や栄養が行きわたり、ホルモンバランスが整いやすくなります。
さらに、脳内の神経伝達物質であるセロトニンの分泌も促進され、自律神経のバランスを乱す要因となるストレスを軽減。この効果から、ホットフラッシュの予防につながります。
そこで、おすすめの有酸素運動と、どれぐらい体を動かせばいいのかをご紹介します。ただし、体調に合わせて運動強度や時間は調整を。無理のない範囲で、少しずつでも続けていくことが大切です。
●おすすめの有酸素運動
・ウオーキング…運動習慣がない方でも手軽に始められ、続けやすいでしょう。
・ジョギング…ウオーキングよりも運動強度が高く、より高い効果が期待できます。
・水泳…全身運動であり、関節への負担が少ないため、運動初心者にもおすすめ。
・ヨガ…呼吸法やポーズによって、心身をリラックスさせ、自律神経を整えられます。
●運動強度
楽に会話ができる、軽く息が弾む程度の運動を目安にしましょう。心拍数で管理する場合は、最大心拍数の50~70%程度がおすすめです。
●運動時間
1回30~45分、週に3回程度を目標にしましょう。運動習慣がない方は、少しずつ増やしていきましょう。
★睡眠環境の見直し
睡眠の質を上げるうえで、寝室の室温や湿度は重要です。一般的に快眠をもたらすとされる室温は、夏は25~26度、冬は20~22度前後。湿度は通年50~60%前後が良いとされています。また、冬の室温は低すぎることにも注意が必要です。健康に悪影響を及ぼす可能性があるとして、WHO(世界保健機関)は室温18℃以上を推奨しています。
もちろん、快適と感じる室温・湿度には個人差もあるため、ご自身が快眠できる睡眠環境を把握しておくようにしましょう。
★就寝前の習慣改善
睡眠の質は、就寝前の習慣にも影響されます。
夜、ぐっすり眠るには、自律神経のうち副交感神経を優位にすることがポイントです。副交感神経が優位になると、心身の緊張がやわらぎ、血管が拡張して体温が穏やかに下がり、良質な睡眠をもたらします。さらに、ホットフラッシュの予防や更年期症状の軽減といった効果も期待できます。
そこで、副交感神経が優位になるよう、就寝前に取り入れたいことと、逆に副交感神経を刺激するために避けたほうがいいことをご紹介します。
<就寝前に取り入れたいこと>
●照明を暗めにする
就寝1~2時間前から、間接照明や暖色系のライトに切り替え、部屋全体を落ち着いた明るさに。目安の照度は50ルクス以下といわれています。
●軽いストレッチ
布団の上でできるくらいの簡単なストレッチで、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進しましょう。特に首や肩、股関節周りをゆっくり、20秒以上かけて伸ばすことで、リラックス効果が高まります。なお、激しい運動は、心身を活発化させる交感神経を刺激し、体温を上昇させるので避けましょう。
●瞑想
呼吸に意識を集中する瞑想は、心のざわつきを鎮め、リラックス効果をもたらします。5分程度の短い時間でも効果が期待できます。瞑想アプリなどを活用するのもおすすめです。
●ぬるめのお風呂に入る
38~40℃程度のお湯に10~15分ほどゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になります。42℃以上の熱いお湯は、交感神経を刺激するため避けましょう。
●アロマテラピー
ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のあるアロマオイルをディフューザーで焚いたり、枕元に数滴垂らしたりするのもおすすめです。
上記でご紹介した時間は目安です。試したときに、ご自身が心地よいと感じる時間を見つけてみてください。
<就寝前は避けたほうがいいこと>
●飲酒
アルコールは一時的に血管を拡張させ、体温を上げますが、アルコールが分解されて血管が収縮する際に、かえってホットフラッシュを引き起こしやすくなります。また、睡眠の質を低下させる原因にもなります。
●カフェインの摂取
コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、覚醒作用があります。就寝前の数時間は摂取を控えましょう。
●スマートフォンやPCの利用
スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させ、眠りを誘うメラトニンというホルモンの分泌を抑制します。就寝1~2時間前にはスマートフォンやPCの利用をやめ、読書や音楽鑑賞など、リラックスできる活動に切り替えましょう。

以上、一つでも、ももりん様のお役に立てたらうれしく思います。
セルフケアは、更年期の一時的な不調の改善だけでなく、これから先を健康に、そして美しく過ごしていくためのケアにもなります。また、継続することで効果が表れやすくなりますので、まずは取り入れやすそうなものや続けやすそうなものから、試されてみてくださいね。またいつでもご相談をお待ちしております!
※症状が強く日常生活に支障が出る、セルフケアを実践しても気になる症状に変化がない、などのお困りの状態が続くようであれば、受診を検討されることをおすすめします。
専門医を探される際のご参考といたしまして、一般社団法人日本女性医学学会ホームページ内の「女性ヘルスケア専門医リスト」をご紹介いたします。
更年期障害の治療に力を入れている医師や病院の多くは、患者の話に耳を傾け、つらい症状を緩和するための治療方針を立ててくれます。下記ページより、お住まいの地域ごとの医療機関をご検索いただくことができますのでご参考になさってください。
一般社団法人日本女性医学学会ホームページ
<この記事を監修いただいた先生>
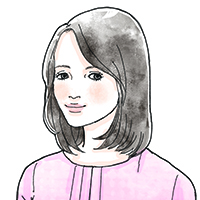
右田 尚子
キッコーマンニュートリケア・ジャパン(株)営業部所属 お客様担当
▼詳しいプロフィールを見る