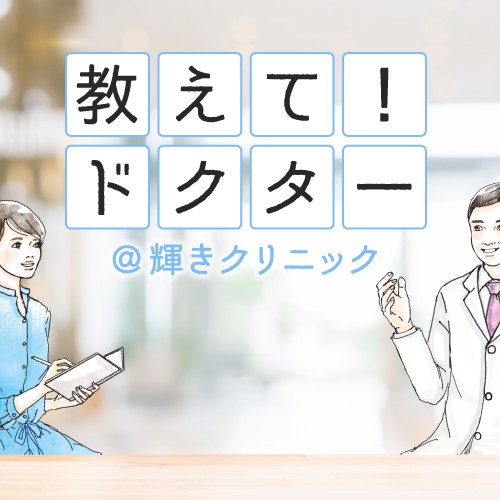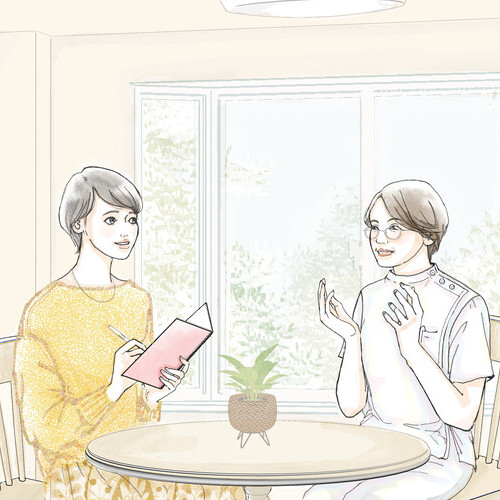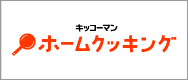更年期から考える介護のハナシ③人とつながり合うことで無理のない介護へ
更新日: 公開日:
学ぶ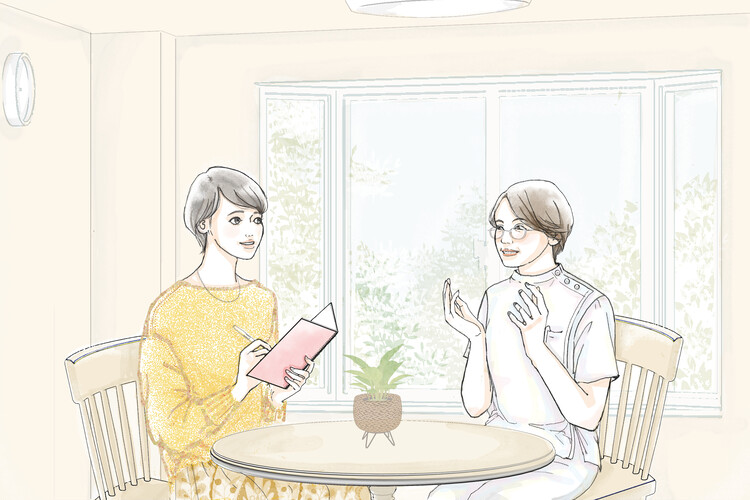
施設のこと、利用できる制度のこと、費用のことなど、介護が始まるとき、分からないことは多くあります。そんなとき、大切なのは一人で抱えないこと。周囲の人や専門家とつながり合うことで、見通しが立ちやすくなることは多いといいます。そこで今回は、春日クリニック院長で、長年更年期女性を応援し続けている清田真由美先生に、お金の話も含めて更年期と介護についてのお話を伺いました(全3回の3回目)。更年期からその先に訪れる老年期を上手に乗り切るためのヒントがいっぱいです!
介護の不安は一人で抱えないこと
―施設選びや費用のことなど、介護について分からないことが多いと、不安になりますね。特に費用のことは気になります。
清田先生(以下、清田) 介護にかかる費用は、その方の疾患の種類や医療依存度、必要とするサービスによってさまざまなパターンがありますので、一概にこれくらいかかる、とお伝えするのは難しいのですが、大切なことは一人で抱えないことです。
介護が始まる際に、かかりつけ医や地域包括支援センター、医療機関のソーシャルワーカーなど、介護費用について相談してみましょう。適切なアドバイスをしてもらうことで、その先の見通しも立てやすくなると思います。
また、医療費、介護費が高額になった場合には、上限を超えた部分が戻ってきたり、税金の控除を受けたりできる制度があります。寝たきりの方の紙パンツ代を助成する制度もあります。どれも、申請が必要です。費用についても、ネットなどで情報を得ることに加えて、ケアマネジャー、社会福祉士、医療機関窓口にご相談されると良いのではないでしょうか。
―一人で抱えずに、専門家のアドバイスを受けることはとても大事ですね。お金についての心配事はみなさんあると思いますし、専門家の方も同様のご相談をきっと多く受けているはずですから、いろいろなお話が伺えそうです。
まだ介護が少し先のことで、知識として費用について考えたいときはどうするのが良いでしょうか?
清田 介護に詳しいお金の専門家の本が今は多くありますから、そうした良書から情報を得ると良いのではないでしょうか。例えば、ファイナンシャルプランナーの方の著書などは、とても参考になると思います。

介護費用をどう捻出していくか
―多くの場合、老後の収入は年金が主になりますので、介護費用が多くなれば家計に重く響きます。女性は男性に比べて年金額が少ない傾向があり、介護費用をどう捻出していくかは、自分の老後においても大事な視点です。
清田 女性は出産や育児、そして介護などによって、働き方が変わることがあります。年金額や老後の資金を減らさないためにも、フルタイムに限らず、楽しみやいきがいも見つけながら、細く長く、仕事を続けていけるといいのかなと思います。
親御さんの介護をされている更年期世代の女性自身も、自分の生活にお金がかかる時期ですし、介護離職をしたり、親御さんの介護にお金を使い過ぎたりすると、自分の老後資金が足りなくなることも考えられます。また、ひと昔前と違い、助け合えるきょうだいも少ないので、一人にかかる負担が大きくなりがちです。
―親の介護生活にかかるお金は、できるだけ親のお金(年金や資産など)でやりくりするなど、お金の管理も含めて、家族で話し合うことが大事ですね。
住み慣れた地域での介護のために
―在宅介護の場合、毎日のように通う通所施設は大切な場所になりますね。先生はどのような経緯から通所施設を作られていかれたのですか?
清田 「ずっと看続ける」をテーマに、かかりつけ医として、地域に根差した医療をするにはどうしたらいいかを考えて、日々奮闘するうちに、必要にせまられて現在の形になっていきました。
最初は、介護保険がまだない時期でしたが、患者さんの親御さんが在宅介護で困っているということを知り、「訪問看護で患者さんの病態や在宅の様子を見てきてもらおう」と、訪問看護を始めました。
介護保険サービスが始まった2,000年から介護のマネジメントの必要性が高まりました。在宅の状況、患者さん、家族の困りごとをよく知っている私たちがマネジメントする方が、よりスムーズだと感じ、数名のスタッフがケアマネジャーの資格を取って、居宅介護支援事業所をスタートしました。運営面では、訪問看護は赤字が続きましたし、居宅介護支援事業は収益事業ではありませんので、大変な時期でした。
それから、医療だけでなく、患者さんやその家族を支えるために、医療との連携がスムーズな介護が必要だと痛感し、介護事業を本格的にスタートしました。そこで立ち上げたのが小規模多機能型居宅介護(小規模多機能)です。
―小規模多機能とは、どういったものなのですか?
清田 通所(デイサービス)を中心に、宿泊(ショートステイ)、訪問介護(ホームヘルプ)も必要に応じて利用できる地域密着型サービス※1です。
小規模多機能は2006年に始まった新しい介護サービスでしたので、当時は見学に行けるところも少なく、スタッフで知恵を出し合い、手探りで取り組みました。
その小規模多機能は、現在は看護小規模多機能となり、医師、看護師、理学療法士、言語聴覚士、介護福祉士が、ワンチームとなって、医療・介護ニーズに応えられる場所になっています。利用者さんからは「楽しみながらリハビリできる」「がんの末期や重症心不全でも安心して預けられる」「排便コントロール※2や褥瘡(じょくそう)管理※3もしてもらえる」と喜んでいただいています。
―住み慣れた地域で利用できる地域密着型のサービスで、医療もできる施設があると助かりますね。
清田 利用者さんは基本的に施設の近くに暮らす方ですから、安心して通えますし、通所に加えて訪問看護や訪問介護・宿泊サービスも利用できます。
看護小規模多機能があることで、ご家族の負担や不安を軽減した在宅での看取りが可能となりました。また、一人暮らしの方でも、ご自宅やサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)で最後まで暮らせるようになりました。そうした点も看護小規模多機能となって良かった点です。
※1 利用者が住み慣れた地域で生活できるように、身近な市町村で提供されるサービス
※2 排便の有無、便の状態(便利や下痢など)を見ながら薬の量を調節したり、排便困難時に、浣腸、座薬などで排便を促したりすること
※3 体重や骨の圧力がかかりすぎることで皮膚にできる傷ができないように、定期的に体位を変えるなど適切なケアを行うこと

介護で必要なのは人とのつながり
―先生は、介護では人とのつながりが大事ということを、常々お話されていますね。
清田 これまで医療そして介護に携わってきて思うのは、最後まで自分らしく生きていくには、お金も確かに必要ですが、人とのつながりがそれ以上に大事だということです。
人とつながり合うことができれば、住み慣れた場所で、必要最小限の介護サービスを受けながら、お友だちと助け合って暮らし、そして、周囲のみなさんに看取られて、安心して旅立つことができます。
そうした人と人との関係性をつくるためにも、住み替えを考えるなら、元気なうちがよいと思います。老後への不安が軽減されますし、その時々の介護度にあったサービスを少しずつ受けながら、自分らしく自立した生活を送ることができます。
そしてなにより、ご自身が元気ですから、移動の自由度も大きく、お友だちもつくりやすいと思います。また、お友だちを助けたり、助けられたりしながら、同じ施設で過ごすうちに、あたたかい関係性もできてきます。女性は人とつながる力が強いのが強みです。
人とのつながりができると、前回もお話ししましたが、仮に認知症が進んでも、周囲の助けを借りて、介護サービスをたくさん受けなくても、暮らしていけるんですね。
一方で、介護度がぐんと上がったり、認知症が進んだりしてから、ぽんと施設に入居しても、その場にいる方との関係性を築くことが難しいことがあり、あたたかい関係性も築きにくい面があります。
また、認知症になると、法的にもご自身でご自宅を売りに出すことができなくなりますから、ご自宅を売ってその資金で住み替えを検討するといったことも難しくなります。
更年期世代へのエール
ー最後に更年期世代の女性に向けてメッセージをお願いします。
清田 これまでのお話のなかで、介護を頑張りすぎないこと、そして親の介護は、自分の介護のリハーサルだと思って取り組むと、心の負担が少し小さくなるのでは、というお話をさせていただきました。
そうしたことに加えて、制度やサービス、テクノロジーなど、いろいろなものが日々変化しています。今、難しいことでも、少し先には手軽にできるようになっているかもしれません。インターネットの普及もその一つですね。
ですので、近未来を考えながら、利用できる技術やサービスがないか、先手先手で、情報を集めるようにすると、ご自身の暮らしをエンジョイできる部分が広がるかなと思います。
ー介護をすることになっても、旅行などにも出かけたいですものね。
清田 そうです。先日も、ある娘さんがお母さんを残して旅行に行くか行くまいか悩まれていたのですが、「ずっと、献身的に介護してきたあなたが、介護疲れをリフレッシュするのを見て、お母さんは喜んでくださるはずですよ。いざというときの覚悟と代理で動いてくれる方を決めたら、安心していってらっしゃい」と伝えて送り出しました。
多くの方は75歳くらいから、自分も介護される側になります。親御さんの介護を経て、いざ自分のしたいことをしようと思っても、足腰が弱くなったり、健康面で難しくなったりすることがあるんですね。
そのときに、「あのとき、ああしておけばよかった…」と後悔しないようにしてほしいと思うんです。介護に一生懸命になりすぎずに、制度やサービス、プロの手を上手に利用して、日々の暮らしを楽しんでほしいなと思います。元気があって動けるうちに、したいことをしないと、もったいないですからね。
そのためにも、正しくて新しい情報を集め続けること、そして、少しずつ介護を自分事として考えていく「心の準備」もしていけると良いのではないでしょうか。
―更年期の今のうちから、親の介護を通じて自分の介護についても考えていくと、その先の戸惑いや不安が減るように感じました。3回にわたり、貴重なお話をありがとうございました。
<この記事を監修いただいた先生>

清田 真由美 先生
医療法人社団清心会 春日クリニック院長
▼詳しいプロフィールを見る
<インタビュアー>

満留 礼子
ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。